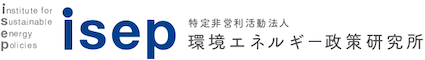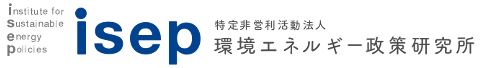第6次エネルギー基本計画への意見および提言(意見・提案)
2021年9月14日
環境エネルギー政策研究所は、以下のとおり国の第6次エネルギー基本計画(案)に対しての意見(パブリックコメント)を提出すると共に、提言「自然エネルギー100%の「エネルギーコンセプト」への抜本的転換を」を発表します。なお、第6次エネルギー基本計画(案)とパブリックコメントの提出先はこちらです。「あと4年 未来を守れるのは今」キャンペーンでは、パブコメへの参加を呼び掛けています。
パブリックコメント意見
| 意見1 | 「原子力の持続的な活用」は止めるべき |
| 該当箇所 | (P23 716〜718行)原子力については、国民からの信頼確保に努め、安全性の確保を大前提に、必要な規模を持続的に活用していく。 |
| 意見内容 | 福島第一原発事故を経験した日本は、原子力は即座にゼロにすべき。国が崩壊するリスクを経験し、十分な安全性も確保されない上に、使用済み核燃料の行き場もない原発を続ける理由がない。 |
| 意見2 | 核燃料サイクル、再処理、プルサーマルは即時廃止すべき |
| 該当箇所 | (P71,2325〜2376行)
b)核燃料サイクル政策の推進 (ア)再処理やプルサーマル等の推進 |
| 意見内容 | 核燃料サイクルは完全に破綻しており、再処理もプルサーマルも即時廃止する。余剰プルトニウムは国際監理下のもとで不動化処理を行う。 |
| 意見3 | 2030年の電源構成:再生可能エネルギーは50%以上とすべき |
| 該当箇所 | (P105, 3562〜3574行)
再生可能エネルギーについては・・・電源構成では36〜38%程度を見込む。 |
| 意見内容 | 再生可能エネルギー、とくに太陽光発電と風力発電は世界史的にコストが急落し急成長しているエネルギー転換の主役(ゲームチェンジャー)であり、この10年間で日本の再エネが10%から20%以上と倍増した過去や、2030年の導入見込み量(3530億kWh)からの上乗せ、電力需要の大幅削減(意見6参照)、ならびに海外(特に欧州)の導入実績(2020年で40%以上)を踏まえ、2030年の電源構成における再生可能エネルギー割合は50%以上をめざすべき。 |
| 意見4 | 2030年の電源構成:原子力はゼロとすべき |
| 該当箇所 | (P105, 3575〜3581行)
原子力発電については・・・電源構成では20〜22%程度を見込む。 |
| 意見内容 | 福島第一原発事故を経験した日本は、原子力は即座にゼロにすべき。
国が崩壊するリスクを経験し、十分な安全性も確保されない上に、使用済み核燃料の行き場もない原発を続ける理由がない。 |
| 意見5 | 2030年の電源構成:石炭・石油等はゼロとすべき |
| 該当箇所 | (P105, 3582〜3591行)
火力発電については・・・電源構成ではLNG火力は20%程度、石炭火力は19%程度、石油火力等は最後の砦として必要最小限の2%程度を見込む。 |
| 意見内容 | 気候危機が深刻化する中、石炭火力や石油火力等は速やかに廃止すべき。
その分は、電力需要の削減と再エネおよびLNG火力でカバーできる。30%程度の変動型再エネに対する電力システムの柔軟性は、LNG火力の調整力、揚水発電や蓄電池、需要側調整力および電力市場で十分に対応することができる。 |
| 意見6 | 2030年の電源構成:電力需要の大幅な削減(3割程度)および各部門の大幅な省エネを見込むべき |
| 該当箇所 | (P104〜107)
(13)2030年度におけるエネルギー需給の見通し |
| 意見内容 | 全般に、省エネルギーの見込み量が不十分(案では2割程度)で4割削減を目指す必要があり、電力需要の削減も3割程度を見込むべきである(案では1割程度)。
電力需要の3割削減(7000億kWh程度)により、再生可能エネルギーの割合を50%以上に高め、原発ゼロ・石炭ゼロの場合でもLNG火力の見込み量を現行と同じレベルの3500億kWh程度(50%未満)とすることができる。この原発ゼロ・石炭ゼロの電源構成により、温室効果ガスの排出削減目標も50%以上の高みを目指すことが可能となる。省エネルギーについては4割程度の削減を目指し、特に建築物(家庭・業務)、産業や運輸の各分野で目標を深堀りして、カーボンプライシングや省エネ法などの規制による対策を強化すべきである。 |
| 意見7 | 電力システム改革:発送電完全分離(所有権の分離)を進めるべき |
| 該当箇所 | (P92, 3091〜3094行)
①脱炭素化の中での安定供給の実現に向けた電力システムの構築に向けた取組 2020年4月に実施された発送電分離により、広域系統運用の拡大、小売・発電の全面自由化及び法的分離の方式による送配電部門の中立性の一層の確保を柱とする、電力システム改革の一連の工程は基本的に完了した。 |
| 意見内容 | 現状の発送電分離(法的分離)は不完全で、実態としては人・情報・資金が自由に操作できるかたちになっているため、たとえば宮崎県延岡市で自治体新電力設立に九州電力が内部情報を使って脅しをかけることが発生している。完全な発送電分離(所有権の分離)を進めるべき。 |
| 意見8 | 電力システム改革:配電部門を所有権分離して、地方公営事業に移管すべき |
| 該当箇所 | (P92, 3091〜3094行)
①脱炭素化の中での安定供給の実現に向けた電力システムの構築に向けた取組 2020年4月に実施された発送電分離により、広域系統運用の拡大、小売・発電の全面自由化及び法的分離の方式による送配電部門の中立性の一層の確保を柱とする、電力システム改革の一連の工程は基本的に完了した。 |
| 意見内容 | 配電部門を所有権分離して地方公営事業に移管することで、ドイツで見られるシュタトベルケ(地方公営エネルギー会社)の形態で地域活性化に活かすべき。 |
| 意見9 | 電力システム改革:容量市場の見直し |
| 該当箇所 | (P75, 2481行など)
(7)火力発電の今後の在り方 容量市場により中長期的に必要な設備容量を確保する。 |
| 意見内容 | 容量市場は、火力発電の維持に使うべきではなく、脱炭素かつ新技術の市場形成となる蓄電池や需要側応答(DR)、再エネに限定すべき。
また、日本型容量市場は非常に高コストで需要家負担が大きく、かつ新電力排除になる不公平な構図であるため、ドイツ型の戦略的予備力、フランスやカリフォルニアの仕組みに倣って、低コストかつ費用効率的で脱炭素技術に限定するべき。 |
自然エネルギー100%の「エネルギーコンセプト」への抜本的転換を
2011年3月11日の東京電力福島第一原発事故から10年を経て、第6次エネルギー基本計画は、当初、2018年に閣議決定された第5次エネルギー基本計画を見直す形で基本政策分科会での審議が行われていた。しかし、2020年10月には2050年カーボンニュートラルが宣言され、さらに2021年4月には温室効果ガス46%削減(さらに50%の高みを目指す)と国際的に宣言されたため、この新たな中長期目標に合わせたエネルギー基本計画の審議が求められた。
ようやく2021年9月に意見募集が始まった第6次エネルギー基本計画(案)では、「再生可能エネルギーに最優先の原則で取り組む」ことが明記され、2030年の電源構成案で自然エネルギー36~38%という、発電電力量で従来の約1.4倍の導入目標が示された。しかし、同時に原子力発電は従来と同じ20~22%を維持するとされため、非化石電源の目標比率は約6割となり、原発の重大なリスクを考慮すれば自然エネルギーだけで6割以上を目指す必要がある。
さらに2050年の想定シナリオの比較検討も行われ、自然エネルギー50~60%で、残り40~50%を原発や火力発電で賄うというシナリオが参考で示されたが、最も実現性の高い自然エネルギー100%のエネルギー供給を目指す世界のエネルギーシナリオの潮流からはかけ離れている[1]。日本においても国内特有の様々な制約条件やグリーン・リカバリーを考慮した自然エネルギー100%のシナリオ[2]がすでに提言されている[3]。
ISEPでは、2018年に現行の第5次エネルギー基本計画に対して、日本のエネルギー政策の中身を根本的に見直すために、原発・石炭を軸とする旧来のエネルギーコンセプトから目指すべき持続可能なエネルギーに向けた新しいエネルギーコンセプトへの抜本的転換のあり方を提言した[4]。そこでの提言の一部はその後、地域主導の分散ネットワーク型エネルギーへの転換として実現されつつあり、自然エネルギーの発電電力量の割合も2020年度には従来の2030年目標に近い21%に達し、原発の割合も4%未満まで減少している[5]。
日本国内では2020年末までに累積で70GWの太陽光が導入され世界第3位となっているが、風力は5GWに留まる。VRE(変動する自然エネルギー)の割合は年間平均で約10%に達しようとしているが、欧州ではすでに平均でVRE割合は20%に達している。日本国内においても九州エリアではVREの出力抑制が2018年から始まっており、自然エネルギーを最優先として、「柔軟性」があり、「強靭」なエネルギーシステムのインフラや電力市場の整備は途上で正にこれからの10年が正念場である。2050年カーボンニュートラルを見据えて自然エネルギー100%で達成するエネルギー政策のための新しい「エネルギーコンセプト」がこの第6次エネルギー基本計画には求められる。
そこで、日本が目指すべき持続可能な社会の実現に向けた自然エネルギー100%の「エネルギーコンセプト」への抜本的な転換のあり方を以下の9項目として提言する。
提言項目
- 自然エネルギー・省エネルギー・地域主導を「三本柱」へ
- 小規模分散型の自然エネルギーによるグリーン・リカバリーを
- ⾃然エネルギー最優先を原則とした導入目標とルールの整備を
- 地域主導・分散ネットワーク型エネルギーとデジタル化への⼤転換へ
- 「3.11 福島第⼀原発事故」の教訓を踏まえた現実的な脱原発を
- 脱石炭の早期実現と柔軟で強靭な電力システムへの規制改革を
- 電力・熱・交通・産業分野のエネルギー統合化と脱炭素化
- 2050年カーボンニュートラルにおける⾃然エネルギー100%への転換
- 情報公開と国⺠参加の開かれた議論の場と政策決定プロセスが必要
1. 自然エネルギー・省エネルギー・地域主導を「三本柱」に
グローバルに進みつつあるエネルギーの歴史的な⼤転換の「三本柱」は、第 1 に⼈類史「第4の⾰命」と呼ばれる⾃然エネルギーの⾶躍的成⻑であり、第2に環境・エネルギー・経済のトリプル・デカップリング(切り離し戦略)を実現しつつあるエネルギー効率化であり、そして第3に⼤規模集中独占型から地域主導・分散ネットワーク型へのパラダイムシフトである。
コロナ禍においては世界全体で経済の停滞によりCO2排出量が前年から6%以上減少したが、自然エネルギーによる発電電力量は7%増加している[6]。⾃然エネルギーの発電コストは太陽光を中⼼に急速に低下しており、2020年までに2010年から8割以上低下している[7]。
世界各国では、この10年間で自然エネルギーの飛躍的な導入が進んでおり、2020年の太陽光や風力発電の年間導入量はコロナ禍にもかかわらず合わせて200GW以上と過去最高に達した[8]。全世界で新規に導入された発電設備の約80%は自然エネルギーであり、そのうち約9割が太陽光および風力発電だった[9]。
エネルギー政策の基本的視点とされている「S+3E(安全性+環境・経済・安全保障)」の実現のためにも、巨⼤リスクを抱える原発への固執を⽌め、原発ゼロを政策決定すると共に、⾃然エネルギーと省エネルギー(エネルギー利⽤効率化)を重視する地域分散型のエネルギーシステムへ転換すべきである。
2. 小規模分散型の自然エネルギーによるグリーン・リカバリーを
小規模分散型の自然エネルギー(とくに太陽光発電)は蓄電池と共に、指数関数的な拡大を継続している。新型コロナウィルスの影響により世界的に経済活動が低迷した結果、2020年はCO2排出量が一時的に減少したが、世界各国で自然エネルギー拡大や省エネルギーを前提としたグリーン・リカバリーに向けた様々な政策が進められており、日本でも小規模分散型の自然エネルギーによるグリーン・リカバリーが求められている[10]。
パリ協定で要請されている世界の平均気温上昇を1.5度以内に抑制するという目標を達成するため、IRENA(国際自然エネルギー機関)やドイツ・エネルギーウオッチなどが提示している中長期の見通しでは、この風力発電と太陽光発電が2050年までに100%を占めるべく、普及の一層の加速化が要請されている。加えて、同じ小規模分散型のエネルギー技術である蓄電池が過去10年でコストが80%減し、その裏返しとして自動車の電動化が加速度的に進んでいる。これらの3つの技術が、原発や化石燃料に取って代わるこれからのエネルギーの主役になる傾向ははっきりとしている。
これからも急速に低コスト化し普及拡大してゆく風力発電・太陽光発電・蓄電池の恩恵を、電力分野だけでなく、輸送交通エネルギーや温熱エネルギーのエネルギー源としても活用するための「セクターカップリング」や「グリーンガス」「グリーン水素」などを視野に入れた、統合的なアプローチが求められている。
ところがエネルギー基本計画案では、「自然エネルギーを最優先に主力電源化」という方向性は掲げているものの、個々の施策は、FIT導入後に急増した太陽光発電が露呈させた初期政策の不備への弥縫策的に対応(太陽光発電の接続可能量と出力抑制、未稼働案件への規制など)と、やはり急増したように見えるFIT制度の賦課金の抑制に力点が入っており、到底、「自然エネルギーの主力電源化」に向けて、速やかな普及に繋がる施策や統合的なアプローチとはいえない。
再エネの市場統合としてFITからFIP(フィードインプレミアム)への移行が2022年度から予定されているが、当日市場やアグリゲーターなどが整っていない日本の電力市場の整備はまだ不十分であり、太陽光発電や風力発電の比率もまだ低い日本の現状を踏まえると拙速であろう。やはり、「自然エネルギーを最優先に主力電源化」を大前提として、以下のような段階的・統合的なアプローチが必要である。
- 自然エネルギーの普及に向けて最大の障害となっている送電系統ルールを抜本的に見直すこと。とくに優先接続や優先給電の確立、コネクト&マネージの原則の確立、一般負担原則の確立、発電側基本料金制度導入方針の撤回など。
- 自然エネルギーの統合に向けて、つぎはぎではなく、根本的かつ本質的な電力市場の見直しと整備を行う。
- 拙速なFIP導入を避けて、現行のFITと入札制度を丁寧に作り込み、海外に比べてコストの高い太陽光発電・風力発電の開発の促進を促す。
3. ⾃然エネルギー最優先を原則とした導入目標とルールの整備を
「純国産エネルギー」である⾃然エネルギーを最優先の原則で基幹エネルギーに位置付け、発電電力量⽐率で2030 年までに⾃然エネルギー50%以上とする意欲的な導⼊⽬標を定めるべきである。
環境・エネルギー・経済のトリプル・デカップリング(切り離し戦略)を前提に省エネルギーにより 2030 年までに約3割の削減で年間電⼒需要を700TWh程度にすると共に、⾃然エネルギーの発電量を 350TWh 以上とすれば⼗分に実現可能な⽬標値である。
第5次エネルギー基本計画では2030 年の⾃然エネルギーの導⼊⾒込量が太陽光の従前からの電⼒系統への接続可能量等の制約条件から 64GW 相当という2020年度末の導入量61GW(ACベース)とほぼ同じ設備容量となっていた。経産省としてあらたな政策強化の目標として100GWとされ、さらに環境省や国交省も巻き込んで野心的水準として120GW程度としているが、これは現状の約2倍に過ぎない。
太陽光は、世界では今や最も安いエネルギー源となり、今後のエネルギー転換と脱炭素の主力となるだけでなく、過去の経験でも短期間に成長することが明らかであることから、少なくとも現状の2.5倍(150GW)程度を目指す導入目標を掲げるべきだろう。⻑期的には 自然エネルギー100%を見据えて現状の5倍以上の300GW 以上を⽬指すべきである。
⾵⼒発電については、これまで10GW という⾮常に低い2030年の導⼊目標が設定されていたが、経産省の政策強化の目標として20GW(陸上16GW, 洋上4GW)としていたが、さらに系統増強等により4GW程度増やして野心的水準を24GWとしている。しかし、すでに 30GW を超える事業の計画が洋上風力を含めてあり、膨⼤な導⼊ポテンシャルや将来のコスト低減を前提とすれば JWPA(日本風力発電協会) 等が提⾔しているように 2030年までに36GW 以上(太陽光の4分の1の設備容量)の⽬標を設定すべきである。さらに⻑期的には 2050年までに150GW 以上(太陽光の2分の1の設備容量)を⽬指すべきである。
これらの⽬標値を実現するためには、電⼒系統などのインフラ整備と共に新たな電力市場を含めたルール整備や規制改⾰など様々な課題を克服する必要があり、そのための新規の設備投資を必要とし、これらは「統合コスト」としてカウントされうるとされている。しかし、さまざまな恩恵のある⾃然エネルギーの導⼊ための「コスト」は、持続可能な未来を実現するためにインフラ投資として⽋かせないと捉えるべきである。さらに⻑期的な視点に考えれば、⾃然エネルギーが純国産でもっとも安いエネルギー源であることから、エネルギーコストの低減と共に化石燃料の削減という大きな便益を得ることができる。
系統接続問題に端を発して定められた太陽光発電や⾵⼒発電の「接続可能量」的な系統接続ルールは、⾃然エネルギーを封じ込めるための「トリック」であり、撤廃すべきであり、現在、九州電力で実施されている自然エネルギー(太陽光、風力)の出力抑制は最小限になるように優先給電ルール等を見直した上で、それでも必要な出力抑制は全て経済的補償をすべきである。
さらに、これまでの電⼒系統の「空き容量ゼロ」や⾼額な「⼯事負担⾦」については、自然エネルギー最優先の原則で、先着優先を見直し、優先接続のルールとして、原則として一般送配電事業者の費用(託送料金)によりプッシュ型で系統を整備することとし、接続する変電所より上位系統の増強費用の負担や、発電側課金は行わないものとする。
化石燃料による火力発電や原発を主力とする既存電源を温存する「容量市場」や「ベースロード電源市場」はその必要性から見直す必要があり、自然エネルギーの最優先を原則として電力システムの柔軟性を確保する新たな電力市場のルールを整備する必要がある。原発を含む非化石電源の価値を取引する「非化石価値取引市場」については、自然エネルギーに特化したグリーンエネルギー市場として抜本的に見直す必要がある。
4. 地域主導・分散ネットワーク型エネルギーとデジタル化への⼤転換へ
世界全体で各地域のステークホルダーが関わる⾃然エネルギーによる地域主導・分散ネットワーク型エネルギー体制(ご当地エネルギー、コミュニティパワー)への⼤転換が進んでおり、ご当地エネルギーと呼ばれる取り組みが全国各地で次々と広がってきている。2016 年 11 ⽉に福島県福島市で開催された「第 1 回世界ご当地エネルギー会議」[11]での「ふくしま宣⾔」では、地域主導のエネルギーへの取組み(ご当地エネルギー)の重要性が謳われている。その中で、コミュニティパワーとエネルギー⾃治の重要性[12]、地域の経済・雇⽤効果への⼤きな効果が期待されている。地⽅の創⽣のためにも、現状の集中独占型から地域主導・分散ネットワーク型への転換は避けて通れない。
また同時並⾏的に進展する電気⾃動⾞(EV)、とくに⼩型バッテリーの技術学習効果による急速な低コスト化や、⼈⼯知能(AI)や IoT(モノのインターネット)、ブロックチェーン、ビッグデータ等を活⽤した「エネルギーのデジタル化」を考慮して、旧来の「⼤規模集中・独占型」のエネルギー産業構造からの構造転換を視野にいれることが⽋かせない。
5.「3.11 福島第⼀原発事故」の教訓を踏まえた現実的な脱原発を
3.11 福島第⼀原発事故の教訓を踏まえた原⼦⼒政策の根底からの⾒直しが⼤前提となる。これまでのエネルギー基本計画と同様に原発を「重要なベースロード電源」と位置付けたこのエネルギー基本計画案は、3.11 以前の「原発神話」をそのまま復活させたものでしかない。2020年度の原発比率はわずか4%未満であり、さまざまな理由から九州や関西など西日本の一部の地域で10基が再稼働しているのみである(その一部も安全対策のため停止)。
柔軟性の低い原発が4基稼働する九州電力エリアでは低需要期に自然エネルギーの出力抑制が全国で唯一実施されている。東日本は、3.11以降、原発ゼロの状態が続いており、電力需給にまったく問題は無い。稼働しない原発は電力会社にとって負の資産となっており、再稼働に向けた安全対策などでその運転コストは増加する一方で、採算のとれない原発から廃炉が進み(すでに24基、17GWが廃炉)、9基は新規制基準の審査に対して未申請である(約10GW)。2030年に20%以上とするには約34GWの原発が稼働する必要があり、そのためには40年を超える炉も含まれるほとんどすべての原発(34GW)を再稼働する必要があり、あまりにも非現実的である。
今なお混沌とした状況の続く福島第⼀原発事故の処理は、半永久的に続くおそれが⼤きい。これまでの経産省の間違った原子力政策のアリバイ作りとして「汚染水処理」に関する海洋放出の問題はその一端である。また、事実上の倒産会社である東京電⼒も、今からでも破たん処理されるべきであり、経営者および規制当局の責任が追求されなければならない。すでに存在する使用済み核燃料の長期保管と処分、廃炉等に伴って発生する放射性廃棄物の処理も大きな課題であり、廃棄物を海外で処理するために輸出規制を見直すことは避けるべきである。さらに本来必要な⽔準の原⼦⼒損害賠償措置への⾒直しを踏まえれば、脱原発こそがもっとも経済的で現実的な選択肢であることは明らかである。
福島第⼀原発事故の被害とその根本原因を⾒据え、事故の実態や後始末の困難さや原⼦⼒規制の実態を深刻に考慮すれば、脱原発を前提とした原発ゼロ社会を⽬指すべきである[13]。そのための具体的な政策として「原発ゼロ基本法案」[14]などを国会においてその実現に向けて真剣に議論すべきである。
さらに脱原発を前提に、廃炉や核のゴミ、実質的に破たんしている核燃料サイクルの後始末など原発が直⾯している難題に向き合って、国⺠的な対話で合意と改善を⽬指す必要がある。
6. 脱石炭の早期実現と柔軟で強靭な電力システムへの規制改革を
早期のカーボンニュートラルの実現に向けて世界ではCO2排出量の大きい石炭火力発電を2030年より早期に廃止することが求められている。エネルギー基本計画案では、非効率石炭火力のフェードアウトなどにより2030年の石炭火力の割合を約19%程度にするとしているが、CO2排出量の削減には2030年までの石炭火力の廃止が極めて有効で合理的な選択肢となる。
脱石炭により火力発電はほとんど全て天然ガスとなり、ガスシフトが進むことになるが、そのためのガス火力発電設備のさらなる効率化や必要な流通や備蓄のインフラ整備、安定した海外からの天然ガス(LNG)の確保が求められる。天然ガス火力の発電効率は60%以上に達するものの、需要側に設置して地域冷暖房などのインフラと統合されたコジェネレーション(熱電併給)によりエネルギー効率を90%以上により高めることが可能である。
自然エネルギー100%に向けて、電力システムの柔軟性や強靭性を高めるために、原発が最優先されている現行の優先給電ルールを見直し、純国産エネルギー源かつ限界費用が最も安い太陽光発電や風力発電が最優先される給電ルールと運用への見直しが必要である。
さらに自然エネルギーのオンライン制御の割合を増やす経済的なインセンティブや電力・熱・交通のセクターカップリングを含む積極的なデマンド・レスポンスの活用など積極的な導入が期待される。
さらに、これまで指定電気事業者の指定を受けた電力会社毎に「接続可能量」が設定され、それを超えた太陽光や風力発電設備については無制限・無保証の出力抑制が求められていたが、これが2021年4月からは都市部を含む全国の電力会社エリアに拡大された。この様な無制限・無保証の自然エネルギーの出力抑制を定める制度を廃止し、出力抑制分を補償するなど制度の見直しが必要である。
なかでも国内で現状で唯一、自然エネルギーの出力抑制が実施されている九州電力エリアでは、自然エネルギーの導入拡大と共に、原発の稼動状況や石炭火力などの最低出力、揚水発電や関門連系線の運用状況により影響を受けており、月ベースでは抑制率が20%を超えるため、今後の導入を促進するためにも無制限・無保証の抑制ルールの早急な見直しが必要である[15]。
7. 電力・熱・交通・産業分野のエネルギー統合化と脱炭素化
3.11以降に進んできた電力システム改革と自然エネルギーの導入においては、主に電力分野が中心となって脱炭素化に向けた取組みが進められてきた。しかし、ガス供給事業や熱供給事業の自由化も徐々に進められてきたが、脱炭素化への取組みは進んでいない。
交通分野での脱炭素化の切り札とされる電気自動車の普及もまだ始まったばかりであり、膨大な熱需要のある鉄鋼・セメント・化学工業など重厚長大産業を中心に産業分野においても脱炭素化への取組みは長期的なビジョンの策定に留まっている。
2030年46%排出削減や2050年カーボンニュートラルに向けては、電力分野だけではなく、これらの熱・交通・産業分野での脱炭素化を行うためのエネルギー統合化(セクター・カップリング、スマートエネルギーシステムなど)のための市場づくりやインフラ整備が重要である[16]。
そのインセンティブとなるカーボン・プライシングの制度づくりと市場へ構築を急ぐ必要がある。熱分野での脱炭素化においては、地域熱供給のインフラシステムの構築が重要な役割を果たすことが欧州での事例や研究などで示されている[17]。
8. 2050年カーボンニュートラルにおける⾃然エネルギー100%への転換
このエネルギー基本計画案では、2050年カーボンニュートラルの実現向けて電力部門は、自然エネルギーと合わせて実用段階にある脱炭素電源として原子力を活用するとしている。しかし、原子力発電は、福島第一原発事故で証明されたように誰もその安全を担保することはできず、原子力規制委員会も一定の水準の規制基準への適合を審査しているにすぎない。
本当に安全を最優先するのであれば原子力発電の再稼働はせずに、廃炉を進めることが多くの国民の理解を得られる選択である。国、産業界、立地地域がこれまで原子力に費やしてきた資産を清算し、原発の廃炉と共に使用済み核燃料の処分方法を決めていく必要がある。
2050年カーボンニュートラルに向けて自然エネルギーを100%活用するためには、熱分野や交通分野とのシステム統合(セクター・カップリング)の仕組みやインフラの構築が重要となる。さまざまな蓄電技術(揚水発電、蓄電池など)に加えて、ヒートポンプによる熱への変換(P2H)や蓄熱、電気自動車へのスマートな充電や系統への放電(V2G)などが地域分散型のシステムで行われる。
蓄電できない余剰の自然エネルギーは水素に変換され、燃料電池(熱電併給)や合成メタン(メタネーション)および輸送用の合成燃料として利用されることになるが、その実現は2030年以降になるはずである。水素利用のための研究開発や実証は必要であるが、2030年までのその利用は限定的であり、自然エネルギーの直接利用や流通ネットワークや蓄エネルギーのインフラ整備に力を入れるべきである。水素は、二次エネルギーの利用形態のひとつであり、水素の利用拡大や必要なインフラへの投資は、少なくとも短期的には温室効果ガス排出削減やエネルギー転換のための最優先事項ではない。
火力発電から排出されるCO2を回収して長期的に貯蔵するCCSや合成メタンや合成燃料などの製造のために使うCCUS(カーボンリサイクル)についても、実証段階の技術であり、自然エネルギーのような将来の普及を見通すことは難しい。水素と合わせてアンモニアについても自然エネルギーからの製造や海外からの調達にはコスト面から大きな困難があり、そのような技術を前提としたカーボンニュートラルは一部の産業分野や交通分野など限定的と考えられる。
9. 情報公開と国⺠参加の開かれた議論の場と政策決定プロセスが必要
そもそも2018年のエネルギー基本計画でも示された「原発は重要なベースロード電源」⾃体が、3.11 以前の「原発神話」(安全、安価、安定)をそのまま維持するナンセンスなものであった。さらに、原発⽐率をむき出しで議論することを避けるために、「ベースロード電源」として⼀定⽐率の原発の維持が必要という論理を押し通そうとしている。
なお、欧州などでは「ベースロード電源」という概念が消えつつあり、今回の「国の論理」が時代遅れといえる。こうして振り返ると、国は不透明・不誠実な議論のプロセスを重ねてきており、国⺠参加や透明性ある議論とは対極にあり、今⽇の熟議⺠主主義の時代における政治や政府の姿勢とはかけ離れている。
福島第⼀原発事故を始め、さまざまなエネルギー政策の硬直化を招いた⼀因として政府や独占的な地位にあるエネルギー関連企業による情報の秘匿が考えられる。また、エネルギー政策のような重要な基本政策は、最終的に国⺠やさまざまな主体が関与して合意すべき問題であることから、政府や関連企業は情報を公開する義務を負っているはずであり、政策決定プロセスにおいても多くの国⺠の意⾒が反映される適正なプロセスが担保される必要がある(環境問題においては市⺠参加を担保するオーフス条約の批准なども必要)。そのためには、国⺠の代表者から構成される国会上での⼿続き(熟議)をエネルギー政策の決定プロセスに盛り込む必要がある。
エネルギーの選択は、国の専管事項でもなければ産業界の要望だけで決められるべきものでもない。地域分散型⾃然エネルギーが急速に進み、気候変動問題の⼤きなリスクに直⾯し、そして 3.11 福島第⼀原発事故を経験した私たち⽇本に住むすべての⼈々が参加し、議論し、合意を重ねて選び取るべきものである。
参考資料
- [1] WWF(2021)、Energy Watch Group(2019)、IEA Net Zero by 2050(2021)、IRENA(2021)のシナリオなど参照
- [2] 未来のためのエネルギー転換研究グループ「レポート2030:グリーン・リカバリーと2050年カーボンニュートラルを実現する2030年までのロードマップ」https://green-recovery-japan.org/
- [3] 自然エネルギー100%プラットフォーム「2050年カーボンニュートラルを実現へ 〜自然エネルギー100%実現のビジョン~」https://go100re.jp/2534
- [4] ISEP「エネルギー基本計画への意見~「エネルギーコンセプト」の抜本的転換を」https://www.isep.or.jp/archives/info/10910
- [5] ISEP「【速報】国内の2020年度の自然エネルギー電力の割合と導入状況」https://www.isep.or.jp/archives/library/13427
- [6] IEA “Global Energy Review 2021” https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2021
- [7] IRENA “Renewable Power Generation Costs in 2020”, 2021
- [8] REN21「自然エネルギー世界白書2021」https://www.isep.or.jp/archives/library/13336
- [9] IRENAプレスリリース” World Adds Record New Renewable Energy Capacity in 2020” http://www.irena.org/
- [10] ISEP「地域からの「緑の復興」を〜新型コロナによる3つの危機(経済危機・気候危機・社会分断)を超える〜」https://www.isep.or.jp/archives/library/12694
- [11] 第 1 回世界ご当地エネルギー会議 http://www.wcpc2016.jp/ 2016 年 11 ⽉
- [12] 全国ご当地エネルギー協会ホームページ http://www.communitypower.jp/
- [13] 原⼦⼒市⺠委員会「原発ゼロ社会への道 2017〜脱原⼦⼒政策の実現のために」2017 年 12 ⽉ http://www.ccnejapan.com/?page_id=8000
- [14] 原発ゼロ・⾃然エネルギー推進連盟「原発ゼロ・⾃然エネルギー基本法案」 http://genjiren.com/
- [15] ISEP「九州電力の太陽光発電に対する出力抑制に関する事業者アンケート結果と提言」https://www.isep.or.jp/archives/library/13452
- [16] IRENA “Reaching Zero with Renewables”
https://www.irena.org/publications/2020/Sep/Reaching-Zero-with-Renewables - [17] 第4世代地域熱供給フォーラム https://www.isep.or.jp/4dh-forum/